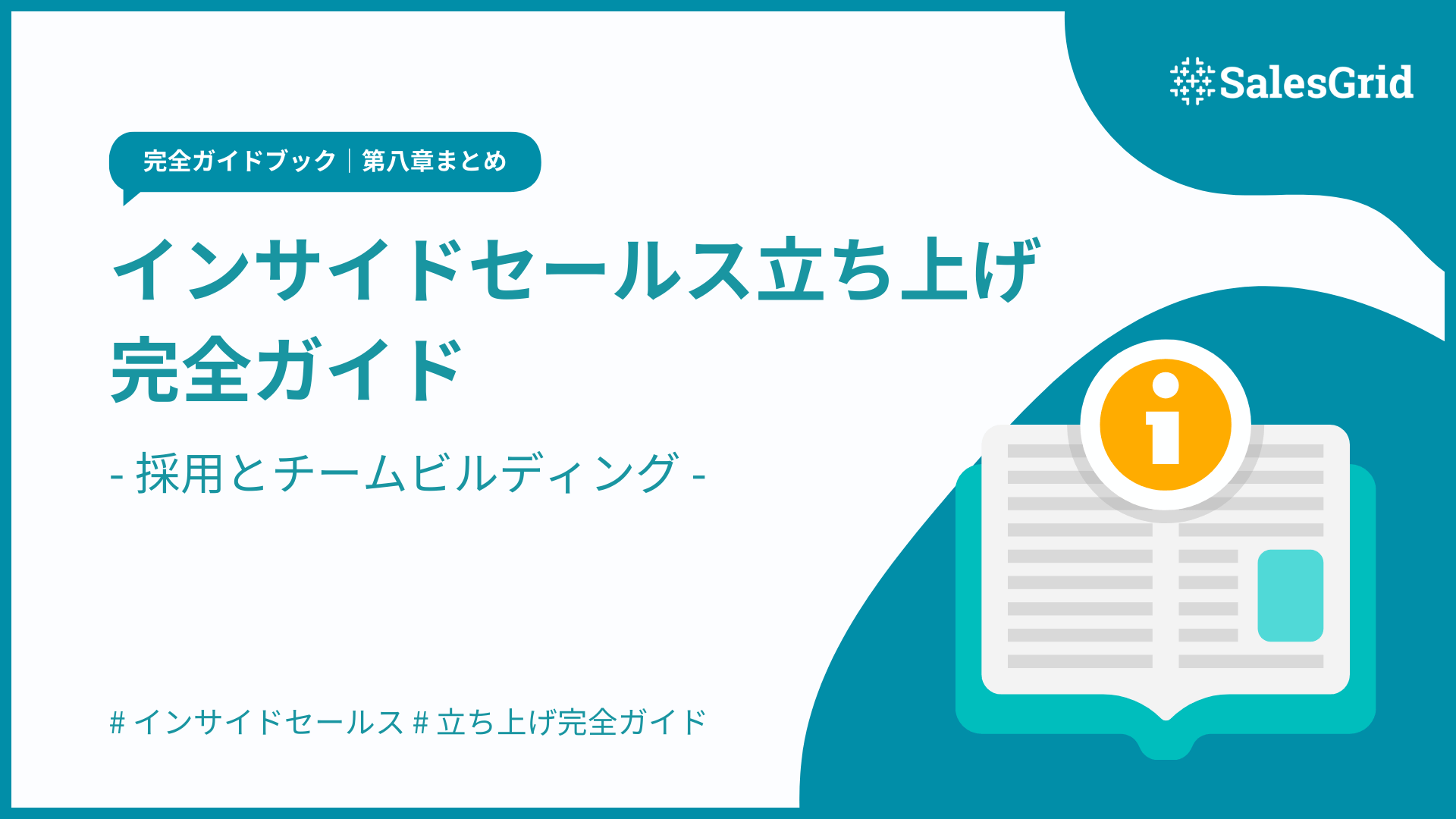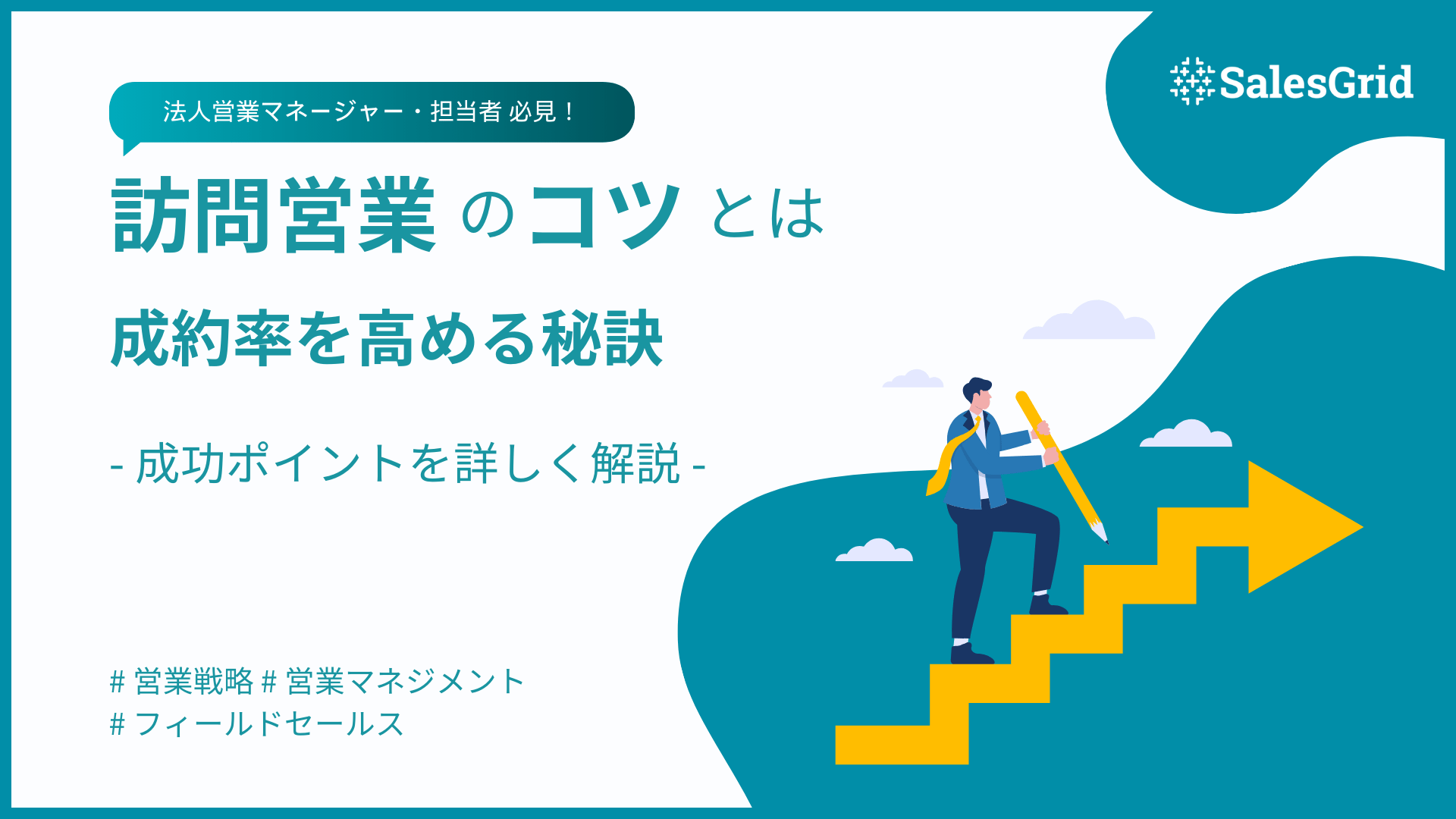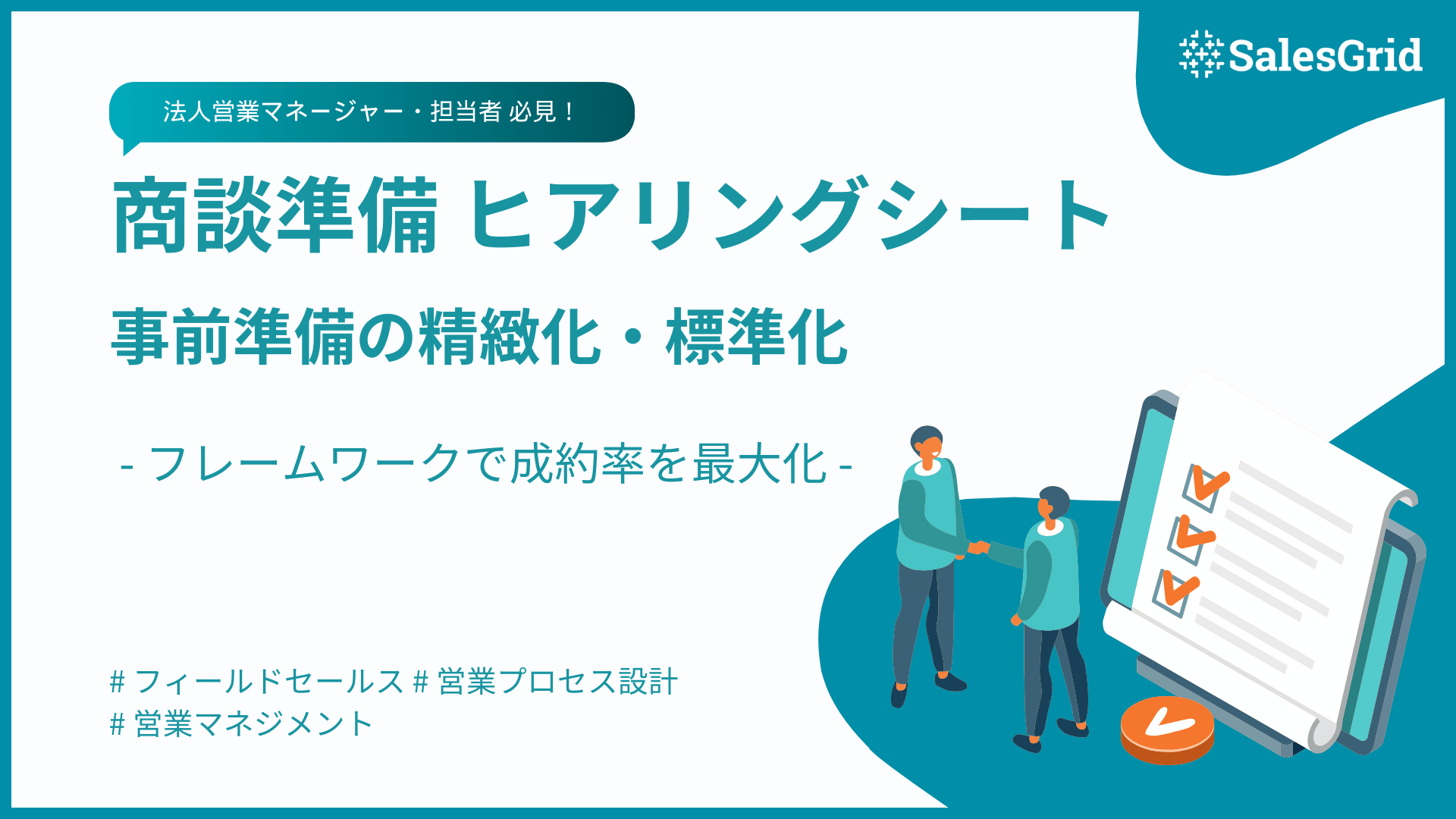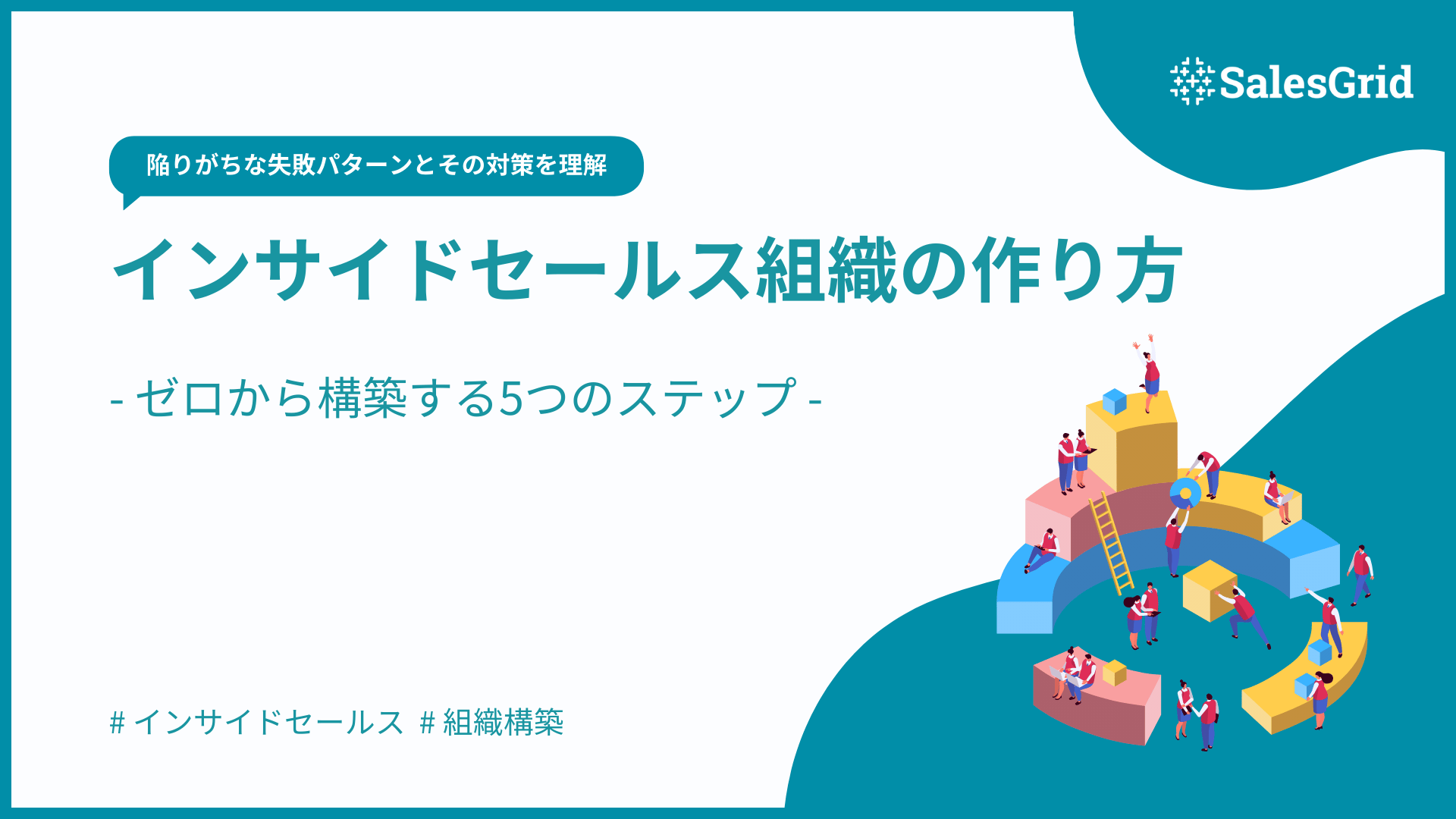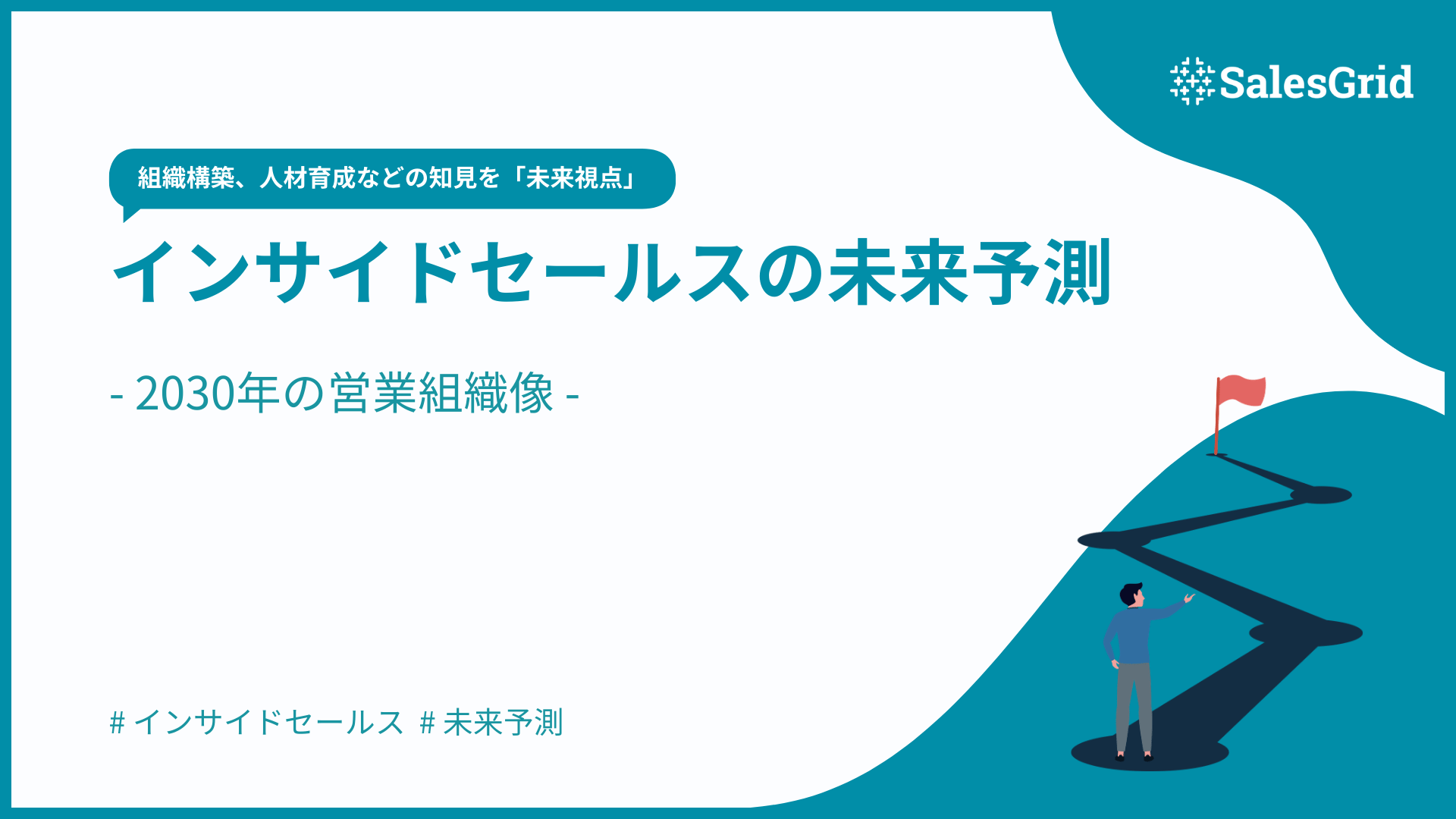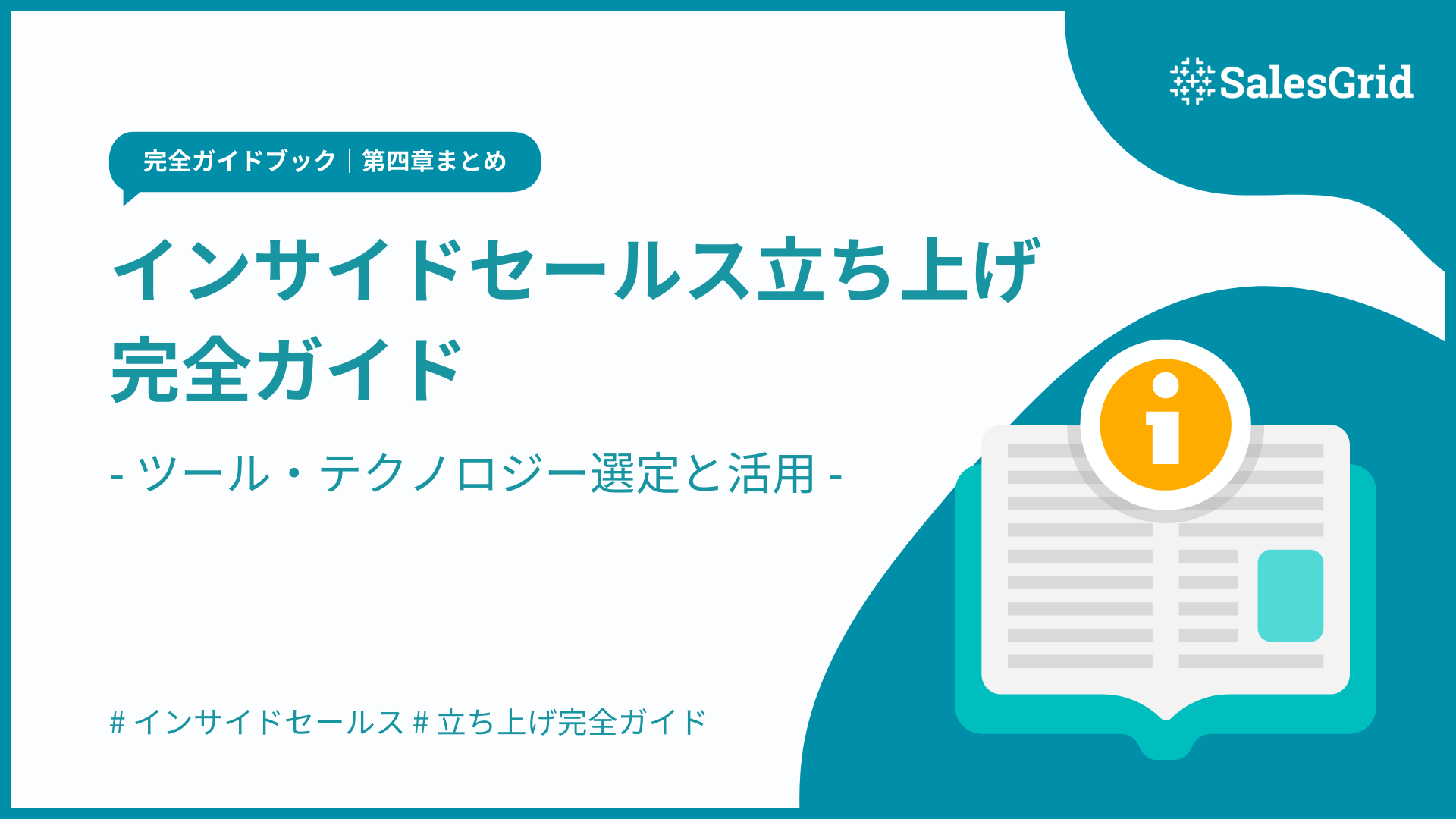BDRのKPI設計が分かる実務手順【チェックリスト付き】
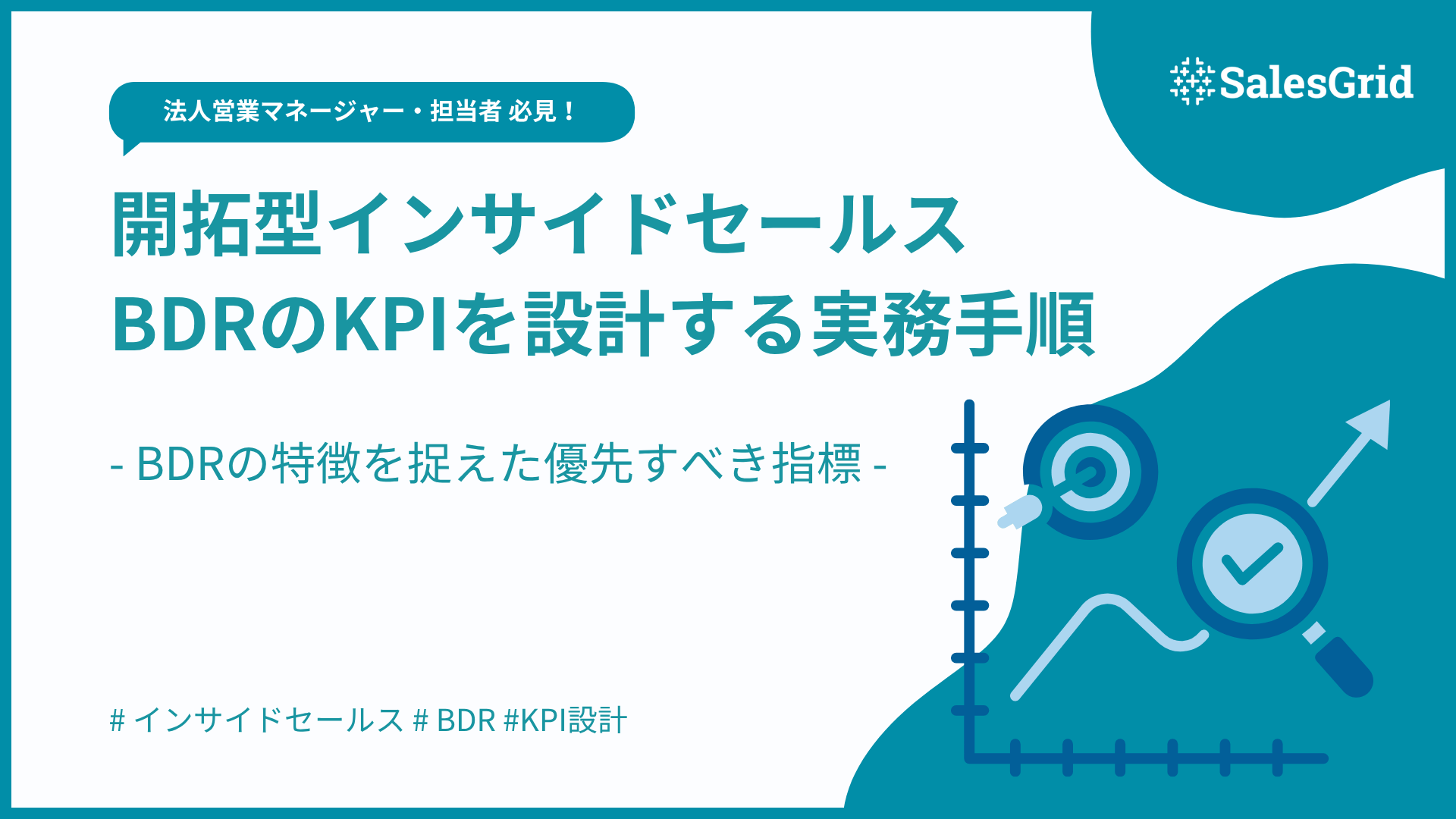
BtoB営業における開拓型インサイドセールス、いわゆるBDR(Business Development Representative)の役割は年々重要性を増しています。しかし、多くの企業ではBDRに対する明確なKPI設計や、KGIとの接続が曖昧なまま活動が進められているケースが少なくありません。

本記事では、KGIから逆算したBDRのKPI設計の実務的なアプローチを解説します。行動・質・成果といった観点からKPIをツリー構造で整理し、週次レビューやSDRとの役割分担、CRMへの反映、フィールドセールスとの連携まで、実際の業務運用をベースに解説します。営業現場で使える設計・改善の手順を可視化し、営業成果につながる体制構築を支援することを目的としています。
BDRの役割とKPI設計の全体像
BDRは見込み顧客との初期接点を創出し、将来的な商談や成約の機会を生み出す役割を担います。SDRやフィールドセールスと連携しながら、ターゲット企業への架電やメール送信、イベント誘致などの手法を駆使して、アポイント獲得や興味関心の醸成を行います。
KPI設計の出発点として重要なのは、企業としてのKGI(最終的な目標)を明確にすることです。BDRのKPIはあくまで手段であり、売上や受注件数といったKGI達成に向けた営業戦略の一部として設計されるべきです。
以下のような観点から、BDRの役割を定義し、KPIの全体設計につなげることが重要です:
- 自社におけるBDRの業務領域(例:エンタープライズ向けの新規開拓)
- 対象とするリードのセグメントやターゲット条件
- SDRや他部門との業務分担の明確化
- ツールやシステム(CRM、SFA)を活用した活動管理の方針
この整理を経て、初めて「どの指標を追うべきか」「どの活動量が適切か」といった数値設計が可能になります。
BDRについて網羅的に理解されたい場合はこちらのBDR Playbook完全ガイドをご一読ください。
👉️BDR Playbook完全ガイド|インサイドセールスによる商談創出・引き継ぎ・最適化の戦略と実践
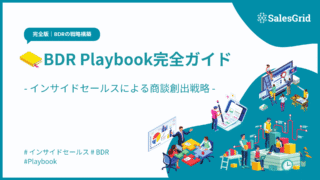
KGIから逆算するBDRの目標設計とアプローチの基本
KPI設計において最も基本となる考え方は、「KGIから逆算する」ことです。最終的な受注や売上といった目標を起点に、必要な商談数、アポイント数、接触数を段階的にブレイクダウンする手法が有効です。
具体的な手順は以下の通りです:
- 自社の平均受注率・商談化率を把握
- 目標受注数から必要な商談数を算出
- 商談化に必要なコネクト数、メール送信数、電話数などを逆算
- 行動ベースでKPIツリーを設計し、週単位の評価指標へ落とし込む
この際、アプローチ方法のバリエーション(テレアポ、メール、SNSなど)ごとに成果の出やすさを検証し、効果的なチャネルを見極めることも重要です。また、業界や企業規模ごとの違いを踏まえて、パーソナライズされたメッセージングを行うことがKPI達成の確度を高めます。
KGIから逆算する数値設計:受注目標、受注率、商談化率、コネクト率を用いた行動量の試算。電話とメールの併用モデルで現実的なKPIを策定します。
数値例:
- 前提:受注目標=12件/月、受注率=20%
- 必要商談数=12 ÷ 0.20 = 60件
- 商談化率=30% → 必要アポイント数=60 ÷ 0.30 = 200件
- コネクト→アポ率=25% → 必要コネクト数=200 ÷ 0.25 = 800件
- 架電→接続率=20% → 必要架電数=800 ÷ 0.20 = 4000コール
チャネル別モデル:
- 電話主導モデル:アポ200件のすべてを電話で創出 → 架電4000コール
- メール主導モデル:メール→アポ化率2% → 200 ÷ 0.02 = 10000通
- 併用モデル(電話60%・メール40%):
- 電話由来アポ=120件 → コネクト=120 ÷ 0.25 = 480 → 架電=480 ÷ 0.20 = 2400コール
- メール由来アポ=80件 → 80 ÷ 0.02 = 4000通
| 指標 | 定義 | 入力値 | 算出式 | 試算結果 |
| 受注目標 | 月間の受注件数 | 12件 | – | 12 |
| 受注率 | 商談→受注 | 20% | – | 0.20 |
| 必要商談数 | 受注に必要な商談 | – | 12÷0.20 | 60 |
| 商談化率 | アポ→商談 | 30% | – | 0.30 |
| 必要アポイント | 商談に必要なアポ | – | 60÷0.30 | 200 |
| コネクト→アポ率 | 有効接続→アポ | 25% | – | 0.25 |
| 必要コネクト | アポに必要な接続 | – | 200÷0.25 | 800 |
| 接続率 | 架電→有効接続 | 20% | – | 0.20 |
| 必要架電 | 接続に必要な架電 | – | 800÷0.20 | 4000 |
| メールアポ化率 | 送信→アポ | 2% | – | 0.02 |
| 必要メール送信 | アポに必要な送信 | – | 200÷0.02 | 10000 |
営業活動の成果は、プロセス全体の設計精度と、日々の行動量・改善の質によって左右されます。目標値は固定ではなく、定期的な見直しとフィードバックを繰り返すことで、継続的なパフォーマンス向上が可能になります。
KPIツリーの構築:成果・行動・質をどう分解するか
BDRのKPI設計においては、「成果」、「行動」、「質」の3つの軸で指標を構築することが基本となります。それぞれの要素を明確に分解し、全体像を可視化することで、日々の営業活動と成果をつなぐ運用が可能になります。
KPIツリー構築の際に意識すべき主な観点は以下のとおりです:
- 成果指標:商談数、案件化数、受注数、パイプラインの創出額
- 行動指標:架電件数、コネクト数、アポイント件数、メール送信数
- 質的指標:接続率、商談化率、ターゲットとの適合度、スクリプト通話の内容評価
特に成果指標だけに偏るのではなく、日々の活動量やコミュニケーションの質も含めた設計が、組織的な成長と継続的な改善につながります。質の指標には、ヒアリング項目の把握率や相手の興味関心レベルの記録といった主観的な要素も含まれるため、CRMなどへの定性データの入力体制も整備する必要があります。
ツールを活用しながらKPIツリーを可視化し、チーム内で共有することが、BtoB営業におけるアクションの一貫性を保ち、最終的な目標達成を実現する鍵となります。
商談化率を軸にした成果指標の設計方法
BDR活動の中で最も重視される成果指標のひとつが商談化率です。これは、アポイントやコネクトなどの接触活動が、どれだけ商談に結びついているかを示す指標であり、営業活動全体の質を測定する重要な数値です。
商談化率を効果的にKPIに組み込むためのポイントは以下の通りです:
- 商談の定義を組織内で明確に統一しておく
- 架電やメールなどチャネルごとの商談化率を分けて集計する
- 商談の発生タイミング(初回接触からの日数)もあわせて分析する
- 業界や企業規模別で商談化傾向をリサーチする
商談化率をKPIの中心に据えることで、単なる行動量ではなく、成果につながる接触の質に焦点を当てた評価が可能になります。また、商談化率が低下している場合には、スクリプトの内容、対象リストの精度、ターゲット条件の見直しなど、改善施策を講じる材料になります。
このように、成果指標を起点としたKPI設計は、BDR活動全体の方向性を示す指標として非常に有効です。改善と検証を重ねることで、より精度の高い営業プロセスの構築が期待できます。
CRM・SFAへのKPI項目の反映と運用体制の構築
KPIを設計しただけでは営業活動の改善や成果には直結しません。現場で運用されるには、CRMやSFAといったツールに指標が正しく反映され、メンバーの業務フローに組み込まれていることが重要です。
そのためには、以下のステップでKPI項目のシステム反映と体制整備を行う必要があります:
- KPIツリーの中でCRMへ記録すべきデータを定義する
- アポイント、商談、フォローアップなどフェーズごとに記録項目を設計する
- 実施中の営業活動に負荷がかからない入力項目数を調整する
- 入力基準や記録のルールをマニュアル化し、教育をセットで進める
- ダッシュボードやレポートの形式を統一し、週次レビューなどで活用する
運用初期は記録漏れや定義のズレが発生しやすいため、チーム内でのフィードバックや定期的な確認を通じて改善していくことが欠かせません。
また、営業部門と開発・情報システム部門が連携し、現場の業務に合った画面設計やデータ項目の追加を柔軟に行える体制も必要です。
項目の設計時に考慮すべき目的と運用上の注意点
CRMやSFAに反映する項目を設計する際は、単に入力する情報を増やすのではなく、「そのデータがどのような分析や改善に使われるのか」という目的を明確にすることが前提です。
設計時に考慮すべきポイントは次のとおりです:
- 「目的達成に直結するか」という視点で項目の必要性を判断する
- 商談化率、コネクト率、対応件数などの主要指標と連動する形で項目を設計する
- マーケティングやフィールドセールスなど、他部門とも共有される情報かどうかを確認する
- 入力者の負担を軽減するため、選択式や自動入力を活用する
また、システムに記録されたデータは、ダッシュボード化やKPIレポート作成に利用されます。分析に耐えうる正確で定義の明確なデータ構造が求められるため、営業支援ツールとの連携や運用フロー全体の整合性にも配慮することが重要です。
こうした運用設計の工夫が、KPI管理の効率化や営業活動の可視化につながり、最終的な成果最大化へと結びつきます。
週次レビューの手順と改善サイクルの回し方
KPIを有効に運用するためには、週次での定期的なレビューと改善サイクルの徹底が不可欠です。数値の可視化だけでなく、現場の担当者とマネージャーが定期的に会話を重ね、現状の把握と具体的なアクション設計を行うことで、継続的な改善と目標達成に近づけます。
週次レビューにおける基本的な流れは以下のとおりです:
- CRMやSFAに記録された数値の確認(KPIごとの推移)
- 目標値とのギャップ分析と原因の共有
- 成果が出ているメンバーのアクション共有(成功要因の可視化)
- 優先順位を定めた改善アクションの設計と担当の明確化
- 次週以降の行動計画とアポイント目標の設定
このようなサイクルを定着させることで、営業活動における改善点が可視化され、部門全体で成果を上げるための共通言語が構築されていきます。
定期的なレビューは、メンバーの活動量やリード状況の変化にいち早く対応できる柔軟な体制づくりにも貢献します。
KPIレビューで注視すべき数値と状況判断の基準
KPIレビューの際に単に数字を見るだけでは、本質的な改善にはつながりません。重要なのは、どの数値に注目し、どのような状況と照らし合わせて判断を下すかという視点です。
注視すべき主な数値項目は以下の通りです:
- コネクト率:架電数に対して有効接続できた割合
- 商談化率:コネクトまたはアポイントから商談へ進んだ割合
- アポ獲得数:ターゲットリストへの接触から日程確定までの件数
- メール開封率・返信率:メールチャネルでの関心度の指標
- 案件発生までの平均リードタイム
これらの数値は、営業プロセスのどの部分にボトルネックがあるかを把握するのに役立ちます。また、数値だけでなく、以下のような「状況」もあわせて確認することが効果的です:
- 送付資料の内容と相手の反応の傾向
- コネクト後の会話内容と興味フェーズのズレ
- ターゲット企業の業界や従来との比較による違い
- 使用スクリプトの改善ポイントやトークのバリエーション
定性情報と数値情報を組み合わせた分析によって、単なる活動量ではなく、商談や受注につながる「質」の改善が見込めるようになります。レビューはメンバーの成長機会であると同時に、組織としての営業戦略をチューニングするための重要なプロセスです。
フィールドセールス連携で成果を高める営業戦略
SalesGridは、顧客の検討段階を「無関心・無認識」から「受注」まで連続するフェーズとして捉え、BDRとフィールドセールスを「COLD→WARM→HOT→MQL→SAL→SQL→Orders」で滑らかに接続します。ポイントは、BDRがアウトバウンドで接点を創出し温度を上げ、「MQLの基準」を満たしたら「SAL」として迅速に引き渡すこと、フィールドが「SQL化→提案→反論処理→クロージング」を担い、失注は理由を明確化して再ナーチャリングのループに戻すことです。図のプロセスに沿った運用により、組織全体のパイプライン効率と受注率を高めます。

- フェーズの可視化:
- 顧客検討フェーズを「無関心→関心→課題認識→解決探索→選択肢評価→担当者合意→決裁者合意→書類チェック→受注」と定義します。
- 温度管理と定義:
- リードは「COLD/WARM/HOT」で管理し、MQLの閾値を営業・マーケティングで統一します。
- 引き渡しの形式知化:
- 「SAL」は受け手が審査可能な単位で作成し、24時間以内の一次対応をSLA化します。
- 失注の戻し先:
- 一次不成立は「NonSQL-Failure」としてWARMやInactiveへ戻し、商談中の失注は「SQL-Failure」として理由分類のうえ再育成へ戻します。
- データの一元管理:
- CRM/SFAでステータスと理由コード、次回アクション、決裁者情報、金額レンジ、導入時期を必須化します。
- フィードバックループ:フィールドからBDRへ「失注理由・勝因・有効トーク」を定例で共有し、リストやスクリプトを継続的に改善します。
リード接続から受注までの連携ステップと役割の整理
SalesGridが推奨する連携は、図の流れに合わせて次の順で標準化します。
- 初回接点と温度付け(BDR)
- Target Accountsをリストアップし、Researchのうえ架電・メール・手紙(DM)・SNSでアウトバウンドアプローチを実施します。New LeadsをPoolに取り込み、反応や会話内容に基づきCOLD/WARM/HOTを更新します。MAやウェビナー招待、資料送付で関心を高めます。
- MQL判定とSAL作成(BDR/SDR)
- MQLの基準を満たしたら「SAL」を起票します。必須項目は次の通りです
- 課題の要約と言語化(現状と解決ニーズ、想定商材)
- 決裁者候補と関与者、組織構造
- 導入時期の目安、金額レンジ、評価基準
- 次回アポイント日時と目的、合意済みの進め方
- 競合状況、これまでの接点履歴、開封・接続ログ
- MQLの基準を満たしたら「SAL」を起票します。必須項目は次の通りです
- Approach SALと一次審査(フィールド/SDR)
- 受領後24時間以内に連絡し、要件の妥当性を確認します。不成立は「NonSQL-Failure」として理由コードを付与し、WARMまたはInactiveへ戻して再育成キューに入れます。成立時は速やかに商談化へ進めます。
- SQL化と商談プロセス(フィールド)
- 「Pitch SQL→Handle Objections→Close」の順で進行します。
- Pitch:課題仮説の検証、価値訴求、評価項目の合意
- Handle Objections:価格・機能・導入体制などの反論処理
- Close:担当者合意→決裁者合意→書類チェックへ進行
- 不成立は「SQL-Failure」として理由を記録し、再アプローチ計画をBDRと共有します。
- 「Pitch SQL→Handle Objections→Close」の順で進行します。
- Ordersとフォローアップ(フィールド→BDR)
- 受注後はオンボーディング計画とアップセル機会を整理し、学びをBDRへ還流します。成功要因をスクリプトやリスト条件へ反映し、次の開拓に活かします。
運用上の指標例は、SAL率、SAL→SQL化率、SQL勝率、NonSQL-Failure/SQL-Failureの理由分布、再接続までの平均日数です。これらを週次でレビューし、温度判定の精度、トーク、件名、時間帯、担当アサインの見直しにつなげます。図のとおり、失注を単なる終端にせず、WARMやInactiveへ計画的に戻すループを設けることが、パイプラインの健全性と受注の最大化に直結します。
成果につながるKPI運用の成功パターンと注意点
KPI設計が理にかなっていても、実際の営業現場で活用されなければ意味がありません。KPI運用を定着させ、成果につなげるためには、成功パターンを押さえつつ、ありがちな落とし穴を回避することが重要です。
まず、成果につながりやすい運用の特徴として、以下のようなパターンが挙げられます:
- KPIが現場の活動内容に合致しており、メンバーが日常業務の延長で記録・確認できる
- 週次レビューやワンオンワンでの継続的な振り返りを通じて、定着と改善の機会がある
- ダッシュボードなどで数値の見える化が進んでおり、チームで共通認識を持てている
- KPIが最終的な営業目標(受注や売上)と連動しており、意義が腹落ちしている
一方、運用が形骸化しやすいケースには以下のような注意点があります:
- 項目が多すぎて入力や管理が煩雑になっている
- 評価のためのKPIとなっており、改善のために活用されていない
- 部門ごとの目標がバラバラで、相互に干渉し合ってしまっている
- マーケティング、BDR、SDR、フィールドなどの間で定義が統一されていない
こうしたリスクを防ぐには、部門をまたいだ目標・KPIの整合性を高めることが必要です。次節ではその方法について具体的に解説します。
部門間の目標連携と指標のすり合わせ方法
営業成果を最大化するには、部門間で目標とKPIを正しく接続させることが不可欠です。マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスなど、複数の部署が関わるBtoB営業においては、各部門が部分最適に陥ると全体のパフォーマンスが低下します。
指標のすり合わせを行う際は、以下のプロセスを踏むことが効果的です:
- 全社KGI(例:月間受注数、売上額)を起点に各部門のKPIを逆算
- 「どの部門が何件のアポイント・商談を創出すべきか」などの目標分担を設計
- 用語や定義(リード、MQL、SQL、商談など)を共通化
- 評価指標をKPIではなく「KPIの改善アクション」に設定する
- 全体会議やプロジェクトチームを通じて、指標の共有と合意形成を図る
また、異なる部門のメンバー間で業務理解を深めるため、ロールプレイや一時的な兼任などの施策を導入する企業も増えています。KPIを単なる管理指標として扱うのではなく、「チーム全体の連携を支えるツール」として活用することで、営業活動全体の効率化と成果向上を実現できます。
チェックリスト:BDRのKPI設計・運用の最終確認
BDRとSDR、フィールドセールスの分業体制で、KPIを日々の営業活動へ落とし込むための最終確認リストです。CRMやSFAのダッシュボードを開きながら、週次レビューの冒頭で確認してください。完了した項目はチェック済欄の□を☑に更新します。
| チェック項目 | 補足説明 | 済 |
| 目的とKGIの定義 | 売上や受注件数など最終目標を数値で明確化し、期間を設定します。 | □ |
| KPIツリーの分解 | 成果・行動・質で指標を設計し、商談化率や受注率の算出式を共有します。 | □ |
| ターゲットとリストアップ | 業界・規模・役職でセグメントし、アカウントと担当者を最新化します。 | □ |
| アウトバウンド設計 | 架電とメールの配分、件名、時間帯、コネクト目標を設定します。 | □ |
| コネクトの定義と目標値 | 有効接続の条件を定義し、日次・週次の目標件数を決めます。 | □ |
| アポイント基準と商談の定義 | アポイント成立条件と商談の判定基準をチームで統一します。 | □ |
| 商談化率・受注率の基準 | 目標値と下限値を設定し、ギャップ時の対処手順を決めます。 | □ |
| 引き渡し条件(SAL→SQL) | SALの必須項目とSLA、SQL化の可否判断をチェックリスト化します。 | □ |
| フィールドアサイン基準 | 金額レンジ、確度、エリアで担当を自動または準自動で割り当てます。 | □ |
| CRM項目の必須化 | 決裁者、導入時期、金額、フェーズ、失注理由を必須入力にします。 | □ |
| SFAダッシュボード | ファネル、チャネル別トレンド、品質KPI、メンバー進捗を可視化します。 | □ |
| 週次レビュー運用 | 議事メモ、改善アクション、担当、期限、次回確認指標を記録します。 | □ |
| 失注理由と再接続設計 | 理由コードを整理し、再アプローチのチャネルとタイミングを決めます。 | □ |
| フォローアップ手順 | メール、手紙、レター、DM、ウェビナーやセミナー案内を標準化します。 | □ |
| マーケ連携とSDRの役割 | リード定義、MQL基準、ナーチャリング手順をマーケティングと統一します。 | □ |
| エンタープライズ対応 | 決裁者マップ、購買プロセス、関与者の情報を顧客管理に反映します。 | □ |
| MA連携とスコア | マーケティングオートメーションの開封・返信・Web行動をKPIに接続します。 | □ |
| スクリプトと件名の検証 | トークとメール件名のA/Bテスト結果を反映し、継続的に改善します。 | □ |
| リソースと優先順位 | 月間キャパ、稼働時間、優先アカウントの配分を見直します。 | □ |
| コンプライアンス | 個人情報、SNS・電話・DMの運用ルールと同意管理を確認します。 | □ |
必要に応じて、表の行は自社のCRMやSFAの項目名に合わせて微調整してください。週次レビューのテンプレートに本チェックリストを貼り付ける運用を推奨します。
まとめ:KPI設計から運用改善まで、BDR活動を成功させる実践手順
本記事では、BDRにおけるKPI設計の全体像から、運用・改善までの実務手順を詳しく解説しました。成果を出すためには、構造的かつ現場に即した指標設計と、部門間連携を前提とした運用体制の構築が求められます。以下に、実務で押さえるべき重要ポイントを整理します。
- KGIから逆算したKPI設計:
- 最終的な目標から必要なアクション数を導き出し、指標に落とし込むことで、営業活動に一貫性を持たせることができます。
- 成果・行動・質の3軸でのKPI分解:
- 成果だけでなく、行動量や接触の質を評価に取り入れることで、現場の改善ポイントが明確になります。
- 商談化率を中心とした成果設計:
- アポイントからの商談化率を基準にすることで、成果に直結する営業活動の精度を高められます。
- CRMやSFAへの項目反映と運用整備:
- 記録項目の目的を明確にし、入力しやすい運用体制を整えることで、データ活用が定着します。
- 週次レビューによる改善サイクルの確立:
- KPIの数値を元に現場の状況を評価し、素早くアクションを見直すことで、継続的なパフォーマンス向上が図れます。
- フィールドセールスとの役割整理と連携強化:
- 情報の受け渡しや対応フェーズの明確化により、受注までのスムーズなプロセスを実現できます。
- KPIを軸にした部門間の目標連携:
- マーケティング、BDR、SDR、フィールドなどの間で目標を接続し、組織全体で一貫した営業戦略を推進できます。
- 定義と用語の共通化による運用安定化:
- 商談やリードの定義を統一することで、数値の意味づけが明確になり、KPIの解釈ズレを防ぎます。
KPIは、営業組織における成果を可視化するための「設計図」であり、「改善の起点」として機能します。現場で実行可能な形で設計し、継続的な振り返りと改善を繰り返すことで、BDRの成果は大きく向上します。日々の営業活動の質を高めるために、戦略的なKPI活用を実践していきましょう。
よくあるご質問
質問:BDRとSDRの違いをどのように理解し、役割分担すべきですか?
回答:BDRは新規開拓を担当し、未接触リードへのアプローチや関係構築が主な役割です。一方、SDRはインバウンドリードやマーケティング施策によって創出された見込み顧客への対応が中心です。役割分担の明確化には、リードの定義や顧客の状況に応じたKPI設計が必要です。両者の違いを理解した上で、営業チーム全体の効率化と成果の最大化を図ることが重要です。
質問:KPI設計時にどのようなツールやシステムを活用すべきですか?
回答:KPIの可視化と運用には、CRMやSFAの活用が効果的です。たとえば、SalesforceやHubSpotなどの営業支援システムを使えば、アクションの記録や商談化率、受注率といった数値をリアルタイムで把握できます。データの一元管理により、レビューや改善施策の精度が向上し、部門間の連携強化にもつながります。
質問:KPIレビューのタイミングと頻度はどのように設定すべきですか?
回答:KPIレビューは週次での実施が理想です。営業活動の改善は短期的なアクションの積み重ねが成果につながるため、月次ではタイミングが遅れる可能性があります。週次で状況を分析し、改善点を反映させることで、受注率や活動量の向上に直結します。また、定期的なフィードバックを通じて、メンバーの意欲やスキルの育成にも貢献します。
質問:KPIの成果が上がらないときに見直すべきポイントはありますか?
回答:成果が上がらない場合は、まずKPIが営業プロセスに適しているかを検証する必要があります。具体的には、アプローチ手法の効果(メール開封率や架電接続率)、リストのターゲティング精度、リードの定義などを見直します。また、スクリプトの内容やアポイント設定の条件に課題があるケースも多いため、トーク内容の振り返りも重要です。改善は定量データと現場の声を組み合わせて進めましょう。
質問:エンタープライズ企業へのBDR活動で特に注意すべき点は何ですか?
回答:エンタープライズ企業では、意思決定のフェーズが長く、関与する決裁者が複数存在するケースが一般的です。そのため、個別対応やパーソナライズされたアプローチが不可欠です。また、リードナーチャリングやセミナーなどのチャネルを活用して、中長期的に接点を維持する戦略が求められます。情報収集の精度を高め、商談機会の創出に向けた継続的なフォローが鍵となります。